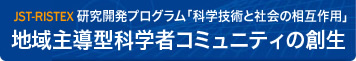| |
生態学者としての研究テーマは、東アフリカ・タンガニイカ湖、マラウィ湖のカワスズメ科魚類(シクリッド類)の自然史、生態、進化、および、ニッチ構築と種間相互作用による生態系進化、生態系サービスの保全と活用を軸とした環境保全論 |
| |
 |
| |
自然環境に関する保全生態学的研究を通じて、環境保全と自然資源管理に役立つ知識を生産すること、その知識を活用した地域住民主体の資源管理と地域振興の方策を考える実践的な「地域環境学」が最近の主な関心。
アフリカの湖から石垣島のサンゴ礁、長野の森まで、さまざまな地域で生態系サービスの保全・創出・活用を通じた地域住民主体の生態系管理と地域振興の両立の方策を検討。環境問題の解決に貢献する科学のありかた、科学と社会の関係に関する考察をすすめている。 |
|
慶応義塾大学文学部卒
上智大学大学院理工学研究科博士後期課程修了
(理学博士) |
国際協力事業団派遣専門家、
京都大学生態学研究センター研究協力員
オーストリア科学アカデミー・コンラート
ローレンツ比較行動学研究所客員研究員
マラウィ大学生物学科助教授
スイス・ベルン大学動物学研究所客員研究員
東京工業大学特別研究員(ヴィクトリア湖岡田プロ
ジェクト)などを経て
2006年4月から長野大学産業社会学部教授
2007年7月環境ツーリズム学部に改組
前WWF(世界自然保護基金)ジャパン自然保護室長
兼WWFサンゴ礁保護研究センター長(2001年10月〜2004年3月)、2008年10月〜
独立行政法人科学技術振興機構・社会技術研究開発センター研究開発プログラム「科学技術と社会の
相互作用」「地域主導型科学者コミュニティの創生」研究代表者
地域環境学ネットワーク 設立発起人
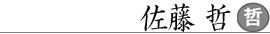 |
|